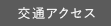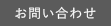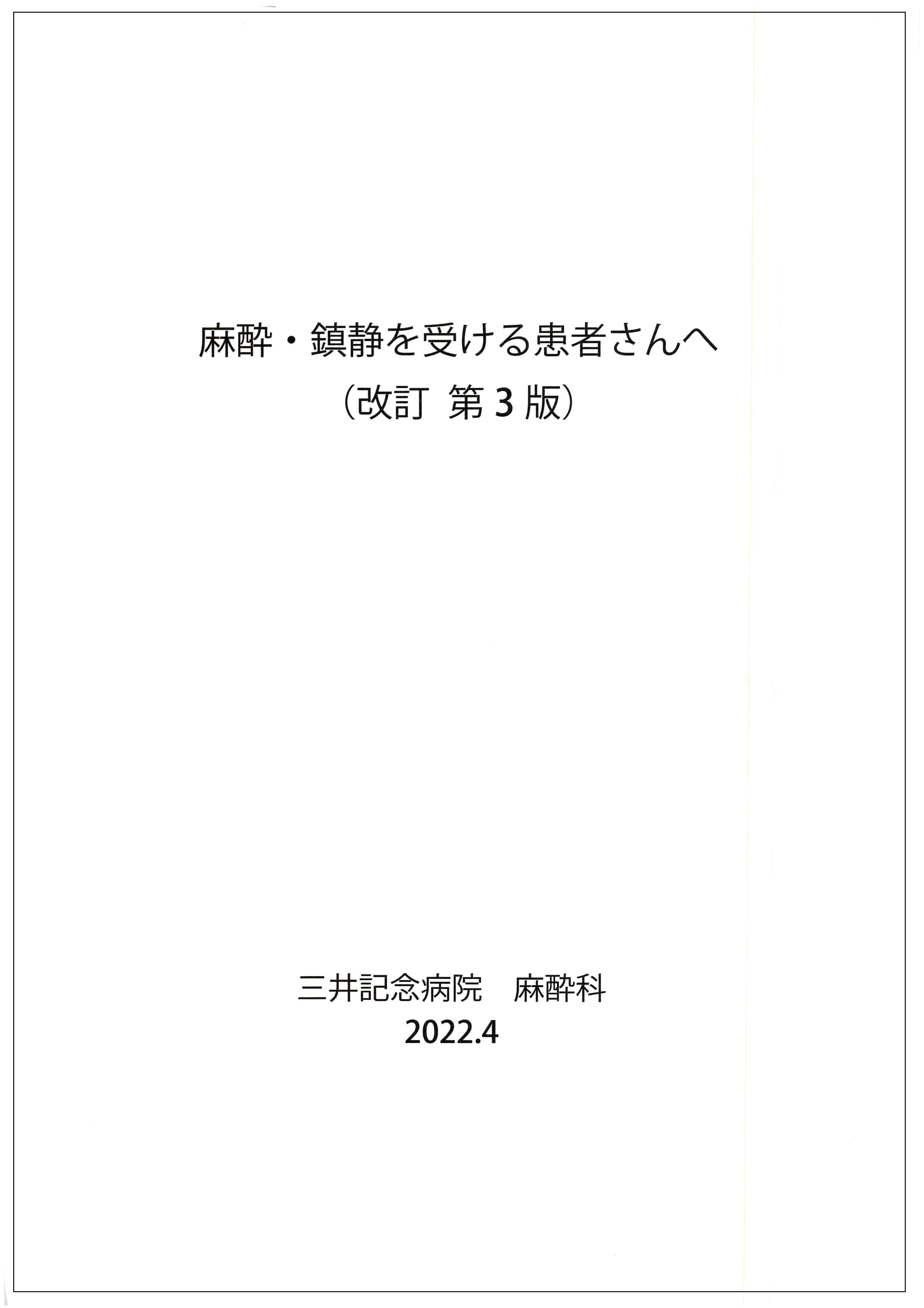麻酔科
診療内容
麻酔と麻酔科医の役割
麻酔は痛みを取り眠らせるだけではなく、手術から患者さんを防御したり、全身の状態を維持することを目的としています。
麻酔科医の最も大きな使命は、手術前・手術中・手術後(合わせて周術期と言います)の患者さんの生命と安全を守ることです。手術には大きな痛みが伴います。痛みは体に大きなストレスをもたらします。この痛みとストレスは手術中だけでなく手術後にも、患者さんの生命や回復に影響を与えます。麻酔科医は循環管理・呼吸管理・疼痛管理などを通じて全身状態を良好に維持管理する専門家です。
麻酔科医の最も大きな使命は、手術前・手術中・手術後(合わせて周術期と言います)の患者さんの生命と安全を守ることです。手術には大きな痛みが伴います。痛みは体に大きなストレスをもたらします。この痛みとストレスは手術中だけでなく手術後にも、患者さんの生命や回復に影響を与えます。麻酔科医は循環管理・呼吸管理・疼痛管理などを通じて全身状態を良好に維持管理する専門家です。
安心して麻酔を受けていただくために
当院ではすべての手術の麻酔を、常勤の当院専属麻酔科医師が担当しています。
患者さんごとに、担当麻酔科医が中心となって麻酔科責任医師らとともに、最も安全と思われる麻酔法を選択します。
手術予定決定後の外来もしくは入院コーディネート室でお渡ししたパンフレット「麻酔・鎮静を受ける患者さんへ」をお読みください。分からないことやご希望は,遠慮なさらずに麻酔科医にお伝えください。
さらに詳しくお知りになりたい方は「日本麻酔科学会ホームページ麻酔を受けられる方へ」をご参照下さい。
患者さんごとに、担当麻酔科医が中心となって麻酔科責任医師らとともに、最も安全と思われる麻酔法を選択します。
手術予定決定後の外来もしくは入院コーディネート室でお渡ししたパンフレット「麻酔・鎮静を受ける患者さんへ」をお読みください。分からないことやご希望は,遠慮なさらずに麻酔科医にお伝えください。
さらに詳しくお知りになりたい方は「日本麻酔科学会ホームページ麻酔を受けられる方へ」をご参照下さい。
診療実績
重症の心疾患、呼吸器疾患、透析などリスクの高い併存疾患を合併している患者さんの麻酔管理を積極的に行っています。また、対病床数あたりの麻酔科管理症例数は全国でも大変高い実績となっています。
また,2023年より術後疼痛管理チーム(Acute Pain Service)を結成しました。麻酔科医、看護師、薬剤師など多職種が協働して、術後の痛みの軽減に努めています。さらに神経ブロックを積極的に併用することで、術後の痛みのコントロールだけでなく、早期離床、早期退院に繋がる麻酔管理を目指しています。
また,2023年より術後疼痛管理チーム(Acute Pain Service)を結成しました。麻酔科医、看護師、薬剤師など多職種が協働して、術後の痛みの軽減に努めています。さらに神経ブロックを積極的に併用することで、術後の痛みのコントロールだけでなく、早期離床、早期退院に繋がる麻酔管理を目指しています。
手術実績
| 年 度 | 麻酔科担当手術件数 | 硬膜外麻酔 | 脊髄くも膜下麻酔 | 末梢神経ブロック | 局所麻酔手術件数 |
| 2023 | 4,770件 | 557件 | 66件 | 342件 | 2,077件 |
| 2022 | 4,722件 | 660件 | 74件 | 396件 | 1,932件 |
| 2021 | 4,614件 | 753件 | 69件 | 411件 | 1,683件 |
| 2020 | 4,373件 | 969件 | 101件 | 601件 | 1,644件 |
| 2019 | 4,842件 | ー | ー | ー | 1,934件 |
| 2018 | 4,092件 | ー | ー | ー | 1,403件 |
| 2017 | 4,387件 | ー | ー | ー | 849件 |
| 2016 | 4,115件 | ー | ー | ー | 3,126件 |
| 2015 | 4,127件 | ー | ー | ー | 5,013件 |
| 2014 | 3,948件 | ー | ー | ー | 5,789件 |
| 2013 | 3,792件 | ー | ー | ー | 6,248件 |
| 2012 | 3,596件 | ー | ー | ー | 5,563件 |
担当医師
部長,中央手術部 部長
横塚 基(よこづか もとい)

学会認定
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
日本心臓血管麻酔学会専門医
4学会合同体外循環技術認定士
日本心臓血管麻酔学会理事・学術委員(体外循環)・専門医試験作成委員
専門分野
心臓麻酔
人工心肺・体外循環技術
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
日本心臓血管麻酔学会専門医
4学会合同体外循環技術認定士
日本心臓血管麻酔学会理事・学術委員(体外循環)・専門医試験作成委員
専門分野
心臓麻酔
人工心肺・体外循環技術
科長
竹内 純平(たけうち じゅんぺい)

学会認定
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
日本心臓血管麻酔学会専門医
日本周術期経食道心エコー認定医
専門分野
術後疼痛管理、心臓麻酔
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
日本心臓血管麻酔学会専門医
日本周術期経食道心エコー認定医
専門分野
術後疼痛管理、心臓麻酔
医長
大槻 達郎(おおつき たつろう)

学会認定
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
日本心臓血管麻酔学会専門医
専門分野
臨床麻酔、心臓麻酔
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
日本心臓血管麻酔学会専門医
専門分野
臨床麻酔、心臓麻酔
医長
佐藤 瑞穂(さとう みずほ)

学会認定
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
AHA認定ACLSインストラクター
AHA認定BLSインストラクター
専門分野
臨床麻酔、心肺蘇生
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
AHA認定ACLSインストラクター
AHA認定BLSインストラクター
専門分野
臨床麻酔、心肺蘇生
医長
今井 恵理哉(いまい えりや)

学会認定
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
日本集中治療医学会専門医
日本心臓血管麻酔学会専門医
日本周術期経食道心エコー認定医
専門分野
集中治療、呼吸療法、心臓麻酔
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
日本集中治療医学会専門医
日本心臓血管麻酔学会専門医
日本周術期経食道心エコー認定医
専門分野
集中治療、呼吸療法、心臓麻酔
医長
田中 真佑美(たなか まゆみ)
学会認定
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
専門分野
臨床麻酔、神経ブロック
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
専門分野
臨床麻酔、神経ブロック
医長
松永 渉(まつなが わたる)

学会認定
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
日本心臓血管麻酔学会専門医
日本周術期経食道心エコー認定医
専門分野
心臓麻酔、産科麻酔
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・認定医
日本心臓血管麻酔学会専門医
日本周術期経食道心エコー認定医
専門分野
心臓麻酔、産科麻酔
医長
山本 麻里(やまもと まり)
学会認定
日本麻酔科学会認定麻酔科専門医・認定医
専門分野
臨床麻酔
日本麻酔科学会認定麻酔科専門医・認定医
専門分野
臨床麻酔
医長
小平 亜美(こだいら あみ)
学会認定
日本麻酔科学会認定麻酔科専門医
日本心臓血管麻酔学会専門医
日本周術期経食道心エコー認定医
専門分野
臨床麻酔
日本麻酔科学会認定麻酔科専門医
日本心臓血管麻酔学会専門医
日本周術期経食道心エコー認定医
専門分野
臨床麻酔
医員
滑川 元希(なめかわ もとき)
学会認定
日本麻酔科学会認定麻酔科専門医・認定医
日本集中治療医学会専門医
日本心臓血管麻酔学会専門医
日本周術期経食道心エコー認定医
米国経食道心エコー認定試験合格
専門分野
臨床麻酔、心臓麻酔
日本麻酔科学会認定麻酔科専門医・認定医
日本集中治療医学会専門医
日本心臓血管麻酔学会専門医
日本周術期経食道心エコー認定医
米国経食道心エコー認定試験合格
専門分野
臨床麻酔、心臓麻酔
医員
仲西 里奈子(なかにし りなこ)
学会認定
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科認定医
専門分野
臨床麻酔
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科認定医
専門分野
臨床麻酔
医員
上條 苑子(かみじょう そのこ)
学会認定
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科認定医
専門分野
臨床麻酔
日本専門医機構認定麻酔科専門医
日本麻酔科学会認定麻酔科認定医
専門分野
臨床麻酔
専攻医
小嶋 太郎(こじま たろう)
学会認定
日本周術期経食道心エコー認定医
日本周術期経食道心エコー認定医
専攻医
太田 俊樹(おおた としき)
専攻医
佐藤 葵(さとう あおい)
専攻医
梶谷 啓典(かじたに けいすけ)
専攻医
一倉 慎矢(いちくら しんや)
研修・採用
| 基 幹 病 院 | 三井記念病院 |
| 連 携 病 院 | 榊原記念病院 |
| 埼玉県立小児医療センター | |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | |
| 東京ベイ浦安・市川医療センター | |
| 前橋赤十字病院 | |
| がん研究会有明病院 | |
| 東京医科大学病院 | |
| 亀田総合病院 | |
| 柏崎総合医療センター |
麻酔科医師採用案内
現在,2025年度開始の専門研修プログラム専攻医を募集しています.
医員(常勤スタッフ)の募集に関しては,三井記念病院医師採用サイトお問い合わせフォームからご連絡ください.
「麻酔科専門研修を希望の方」はこちらへ
医員(常勤スタッフ)の募集に関しては,三井記念病院医師採用サイトお問い合わせフォームからご連絡ください.
「麻酔科専門研修を希望の方」はこちらへ