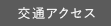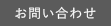一般外科
概要特色
一般外科は消化器外科のスタッフと若手外科医師が診療を担当しており、外科の総合診療科となります。主に虫垂炎、胆石症、肛門疾患(痔疾、脱肛など)、ヘルニア(脱腸)、腸閉塞、その他腹部救急疾患などを対象に手術治療を実施しております。また、外来では刃物で切った指先のけがや、良性のしこりなど、縫う、切除するなど外科的な処置が必要な場合、また、急な貧血・ひどい腹痛・下血や血便など救急手術が必要な場合にも一般外科外来で初診対応しております。どの診療科、専門外来の受付をされるべきかご不明な場合は、あらかじめ受診相談窓口か外科外来にお問い合わせください。
一般外科の外来担当医は外科専攻の若手医師で、消化器外科スタッフ医師の指導のもとで診察いたします。消化器がん、食道裂孔ヘルニア、肝臓や膵臓の嚢胞、大腸憩室など、消化器領域の専門的な治療が必要な病気の患者さんは、消化器外科で受診対応しております。初診の際、一般外科におかかりになった場合でも、当日または後日、消化器外科の外来で専門のスタッフが診察、ご説明いたします。
一般外科の外来担当医は外科専攻の若手医師で、消化器外科スタッフ医師の指導のもとで診察いたします。消化器がん、食道裂孔ヘルニア、肝臓や膵臓の嚢胞、大腸憩室など、消化器領域の専門的な治療が必要な病気の患者さんは、消化器外科で受診対応しております。初診の際、一般外科におかかりになった場合でも、当日または後日、消化器外科の外来で専門のスタッフが診察、ご説明いたします。
主な対象疾患(手術実績は消化器外科のページ参照)
鼠径(そけい)ヘルニア
ヘルニアとは脱出する、という意味の医学用語です。鼠径(足の付け根の内側、前方)から皮膚を押し上げるように何かが飛び出すような膨らみを感じるようになり、ご自身で気づくのがきっかけで診断されます。腸や大網(胃に垂れ下がる脂肪組織)が、お腹の筋肉の隙間から飛び出してくる状態で、一般的には出たり戻ったりの繰り返しとなりますが、戻らなくなると(かんとん:嵌頓)、脱出した腸などが締め付けられて血行不良となり壊死することがあります。嵌頓したことがない場合でも、大変不快な症状となることが多く、手術が強く推奨されます。
手術は最近ではほとんどが人工素材(シリコンシート)を用いて筋肉の隙間を塞ぐ方法が採用されています。腹腔鏡手術、鼠径切開(約5cmのキズ)による手術どちらも対応しております。前日入院で入院期間は3泊程度です。
手術は最近ではほとんどが人工素材(シリコンシート)を用いて筋肉の隙間を塞ぐ方法が採用されています。腹腔鏡手術、鼠径切開(約5cmのキズ)による手術どちらも対応しております。前日入院で入院期間は3泊程度です。
その他のヘルニア:臍ヘルニアや手術のキズからのヘルニアなど
鼠径以外にもお腹の筋肉の隙間から腸や大網が飛び出す病態があります。やはり人工素材を用いる手術を推奨しています。
胆石症、胆嚢炎
胆嚢は肝臓で血液中から濾し出された胆汁を貯めておく場所で、鶏卵よりやや小さいサイズの袋状の臓器です。胆汁は水と油が混じったような組成で、コレステロール、胆汁酸、ビリルビンが3大要素なっており、成分のバランスが崩れる、胆嚢の機能が落ちるなどで結晶が生じると結石(胆石)を作ります。胆石があるだけで手術は推奨しませんが、石が流れ出して詰まるなどのトラブルや胆石疝痛と呼ばれる食後のひどい腹痛などがある場合は手術をお薦めします。また、胆嚢に細菌感染が起こり発熱と痛みがひどい場合も手術が必要となります。手術では胆石のみを除去するのでのはなく、胆嚢を切除することが必要となります。95%以上のケースで腹腔鏡手術により実施しています。
虫垂炎
臍の右下に鋭い痛みを覚えて来院される方は虫垂炎をまず疑います。虫垂とは大腸と小腸の境界近くの大腸に、その「しっぽ」のようにくっついています。虫垂のくっついている大腸には盲腸という名がついているので、虫垂炎のことを一般の方は「もうちょう」と呼んでいます。虫垂は4−8cmくらいの細長い腸ですが、行き止まりとなっており感染しやすく、主に腸内の細菌により虫垂炎を起こします。虫垂が少しむくむ程度の軽症の虫垂炎もありますが、感染した虫垂は破れることもあり、ウミのたまりを抱えるなど、複雑性虫垂炎と呼ばれる重症の病態となることもあります。手術では腹腔鏡により虫垂を切除しますが、多くの場合は抗生剤治療と絶食による腸管安静により手術なしで軽快します。ただし、手術により切除しない場合は、2度目、3度目の虫垂炎となることもしばしばあり、また、抗生剤治療中に高熱をきたす、ウミがお腹の中で広がり痛みがひどくなるなどの場合は方針を変更して緊急手術が行われることもあります。当科では患者さんの要望を伺ってから、初回の虫垂炎は絶食と抗生剤で入院治療し、良くなったら退院2、3ヶ月以降に予定して手術するケースが一番多いですが、患者さんの希望によってはすぐに手術するケース、または、以後も手術を行わないケースもあります。
腸閉塞(イレウス)
腹部の手術、とくに帝王切開や虫垂炎の手術など下腹部の手術の術後の影響で、小腸が癒着により不自然に固定されると、腸がねじれたり折れ曲がったりして、腸が詰まる、すなわち、消化液がせき止められる病態となることがあります。このほか、お腹の中の何らかの窪んだ部分に腸がはまる、がんなど腫瘍のために腸が詰まることで腸閉塞になることもあり、腹部手術の経験のない方にも起こりえます。食べ物以外の嘔吐、特に便の匂いのする茶色や緑色の吐物を吐いた場合は腸閉塞を起こしている可能性が高いです。腸が詰まっている部分より上流に当たる腸や胃の内容液を、鼻から挿入するチューブで抜き取ることにより減圧して軽快することが多いですが、腸の血行不良が疑われる、なかなか軽快しない、一年に何度も入院する場合には腹腔鏡または開腹手術を推奨することもあります。基本的には腸閉塞を起こしている急性期に緊急で手術を行うことが多いですが、何度も繰り返す方は、腸閉塞が軽快した後に予定を立てて手術をすることもあります。
肛門疾患(痔、脱肛など)
内痔核と呼ばれる、出血と脱肛症状(排便後に肛門の粘膜が飛び出すので自身の手で押し戻すような場合)が主体の痔に関しては多くの場合、塗り薬での治療を行っています。内痔核のうち大きくなり過ぎたものや出血が治らない場合は手術を実施しますが3泊程度の入院で行える規模の小さな手術となります。
脱肛症状がひどい場合、子宮や膀胱も脱出してくる場合などは大腸外科で専門的な手術治療をお受けいただけるようにご案内します。
*一般外科では上記の疾患に関して日帰り手術を実施していませんので、全て入院での手術となり、ほとんどの場合は全身麻酔で手術を実施しております。
脱肛症状がひどい場合、子宮や膀胱も脱出してくる場合などは大腸外科で専門的な手術治療をお受けいただけるようにご案内します。
*一般外科では上記の疾患に関して日帰り手術を実施していませんので、全て入院での手術となり、ほとんどの場合は全身麻酔で手術を実施しております。
院長,外科部長
川崎 誠治(かわさき せいじ)

学会認定
日本外科学会外科専門医・指導医
日本肝臓学会肝臓専門医
日本肝胆膵外科学会肝胆膵外科高度技能指導医
日本消化器外科学会消化器外科指導医
日本消化器病学会消化器病専門医
専門分野
肝胆膵外科
日本外科学会外科専門医・指導医
日本肝臓学会肝臓専門医
日本肝胆膵外科学会肝胆膵外科高度技能指導医
日本消化器外科学会消化器外科指導医
日本消化器病学会消化器病専門医
専門分野
肝胆膵外科
部長(消化器外科・がん診療センター)
森 和彦(もり かずひこ)

学会認定
日本外科学会外科専門医・指導医
日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
日本食道学会食道外科専門医
日本食道学会評議員
da Vinci System training as a Console Surgeon
専門分野
食道外科
日本外科学会外科専門医・指導医
日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
日本食道学会食道外科専門医
日本食道学会評議員
da Vinci System training as a Console Surgeon
専門分野
食道外科
心臓血管外科 科長, 医療安全管理部 部長
三浦 純男(みうら すみお)

学会認定
心臓血管外科専門医
外科専門医
胸部ステントグラフト実施医・指導医
腹部ステントグラフト実施医・指導医
経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)実施医
専門分野
大血管・末梢血管血管内治療(ステントグラフト)、
経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)、
透析アクセス手術
心臓血管外科専門医
外科専門医
胸部ステントグラフト実施医・指導医
腹部ステントグラフト実施医・指導医
経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)実施医
専門分野
大血管・末梢血管血管内治療(ステントグラフト)、
経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)、
透析アクセス手術
呼吸器外科 医長,高度治療室 科長
星野 竜広(ほしの たつひろ)

学会認定
日本外科学会外科専門医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医
日本禁煙学会認定禁煙指導医
専門分野
呼吸器外科
日本外科学会外科専門医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医
日本禁煙学会認定禁煙指導医
専門分野
呼吸器外科
専攻医
小粥 進太郎(おがい しんたろう)
竹原 琴音(たけはら ことね)
奥村 兼汰(おくむら けんた)
松本 貴恵(まつもと きえ)
小田 祐一郎(おだ ゆういちろう)
平田 知也(ひらた ともや)
安田 創(やすだ そう)
天野 健一(あまの けんいち)
松本 崇弘(まつもと たかひろ)
竹市 光希(たけいち みつき)
三木 爽慈(みき そうじ)
外来診療表
当科の外来診療表はこちらからご覧いただけます。
外来診療表はこちら
外来診療表はこちら