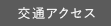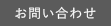形成外科・再建外科
![]()
2024年10月16日 部長 棚倉医師・科長 倉元医師が共同執筆した『乳房再建ガイドブック』が出版されました
![]()
2022年7月13日 乳がん治療の特設サイトを公開しました
![]()
2021年2月23日 市民公開セミナー「がん医療と形成・再建外科 -乳房再建を中心に」Web限定公開のお知らせ
概要特色
形成外科とは、身体に生じた組織の異常や変形、欠損、あるいは整容的な不満足に対して、あらゆる手法や特殊な技術を駆使し、機能のみならず形態的にもより正常に、より美しくすることによって、みなさまの生活の質 "Quality of Life" の向上に貢献する、外科系の専門領域です。
形成外科で扱う疾患は下記に大別されます。
形成外科で扱う疾患は下記に大別されます。
主な対象疾患
再建ー失ったものを取り戻すー
悪性腫瘍の治療を目的とした切除術や、大けがの結果として体の一部分を失うことがあります。形成外科では、顕微鏡下手術(マイクロサージャリー)をはじめとした高度な技術を用いて、失ったものを取り戻し、生活を取り戻すお手伝いをしています。
乳房再建
乳がんの治療により失われた乳房を取り戻す手術です。
乳房再建手術の時期により一次再建と二次再建に分けることができます。また、自分の組織の移植(自家組織)によるものとインプラントによるものに大別されます。
①一次再建(同時再建)
乳がんの手術と同時に乳房再建術を始める方法です。当院ではティッシュエキスパンダー(組織拡張器)を乳がんの手術に引き続いて入れ、手術後、半年以上の期間をかけて皮膚を伸ばし、シリコーン・インプラントやご自身の組織に入れ替えて乳房を再建します。乳がん手術後にすでにある程度のふくらみができており、徐々に大きくできるため乳房の喪失感が少ないことや、2回分の手術が1回で終わるため、手術回数が少なくて済むことがメリットです。一方でエキスパンダー挿入術の合併症(感染による取出しなど)が二次再建よりも多少多くなることが知られています。また、エキスパンダーと放射線治療の相性が良くないことから、当科では術後に放射線治療を要さないと思われる病期の方を一次再建の対象としています。
手術をあまり急がなくてもよい性質の乳がんの方には、乳癌手術と同時にご自身の組織で再建をする方法もあります。詳しくは外来主治医にご相談ください。
②二次再建
乳がんの手術が終わったあとで、時期を改めて乳房再建に着手する方法が二次再建です。全乳房切除後の再建や、部分切除術(温存術)後の変形の修正を含みます。再建方法はさまざまであり、乳房の大きさや治療の経過により、おすすめできる方法は変わります。一回の手術で済む方法や一次再建同様に2回の手術に分ける方法、複数回の脂肪吸引・注入により再建する方法等があります。乳腺科主治医の判断のもと、何年経過しても再建は可能ですので、ご相談ください。
[乳房再建の方法]
1)人工物による再建(シリコーン・ブレスト・インプラント法)
シリコーン・ブレスト・インプラントを使って乳房を再建します。
手術時間や入院期間が短く、からだのほかの部位に傷をつける必要もないなど、負担が少ない点が最大のメリットです。一方であくまで自分の体ではない「異物」であり、ひとたび細菌感染をおこすと(数%の頻度)交換や取り出す手術が必要となります。
また、長期に見ると硬くなったり(被膜拘縮)、壊れたりすることも事実です。また、従来のテクスチャードタイプ(表面がざらざら)のインプラントでは、低率ながらも特殊なリンパ腫の発症があることがわかってきたため、2019年7月に新規の販売が停止されました。
当科では、その後発売されたスムースタイプ(表面がつるつる)のインプラントとテクスチャードタイプのインプラントを用いた再建を提供しております。なお、現在従来型のインプラントが挿入されている方については、世界的にも経過観察が標準的です。
詳細は【こちら】をご覧ください。
2)自家組織による再建
自分の組織を移植して、乳房を再建する方法です。
手術時間や入院期間はシリコーン・ブレスト・インプラント法と比べて長くなります。からだの他の部位にキズをつけることとなりますが、人工物と異なり、劣化したり、破損したりすることがありません。負担は大きい分、「一生もの」の再建ということができます。
組織を移動する際に、一度切り離して顕微鏡下に血管をつなぐ手技が必要になる術式が多いのも特徴です。この血管が詰まり、移植した組織が生着しない可能性が2~3%あります。
当院で行っている再建法には以下の方法があります。
・下腹部の皮弁
おなかの中心寄りにある、腹直筋の中を通る血管とその枝を取り出し、へそより下の皮膚と皮下脂肪を移植する方法で、深下腹壁動脈穿通枝皮弁(DIEP皮弁)と呼ばれています。腹直筋の大部分は温存されます。最も多くの組織量を移動することができ、万能な方法と言えます。大きな乳房や下垂のある乳房にも十分対応することができます。反面キズは30cm以上であり、比較的負担が大きいと言えます。また、生涯で一回しか取れませんが、左右同時であれば半分に分けて両側の再建も可能です。おなかに帝王切開や虫垂炎等、手術のキズがある方でも(タテでもヨコでも)対応可能である場合がほとんどですのでご相談ください。
・大腿内側の皮弁
太ももの内側から後方の、ややたっぷりとした組織のある部位を移植する方法です。代表的なものとして、大腿深動脈穿通枝皮弁(PAP皮弁)があります。負担が比較的軽く、左右2つの組織が採取可能であることが特徴です。DIEP皮弁に比べると、移植できる皮膚や組織の量は少ないため、比較的小ぶり~中くらいの大きさの乳房の再建にむいています。
・腰の皮弁
骨盤の後ろ付近の組織を移植する方法です。組織量に個人差があり、おなかにほとんど厚みがない方でも十分な量の組織が得られる場合があります。腰動脈穿通枝皮弁(LAP皮弁)と呼ばれます。つけられる皮膚量が少ないため、エキスパンダーを挿入してからの入れ替えにむいています。血管の長さは短く、血管の移植を要する場合もあります。おしりの上のほうの感覚が鈍くなることがあります。
・背中の皮弁
背中の筋肉である広背筋を用いた皮弁です。広背筋は失っても日常生活に支障はないとされています。中程度までの大きさの乳房の再建に適しています。血管をつなぐ手技がなく、手術手技としては比較的簡便です。上の3つに比べ、筋肉を一つ犠牲にすることが特徴で、移植後使われなくなる筋肉がやせていくため、最終的な大きさの予測がやや困難であると言えます。
以上、乳房再建について時期や術式の違いにより説明してまいりました。
ライフスタイル、ライフステージによって、乳房再建の目的と、それにかけられる時間は様々です。今の自分に最も適した再建方法を選択するお手伝いをし、提供することを目指しています。
リンパの再建
リンパ浮腫の症状の軽減を目的とした再建術です。
上肢では主に乳がんの治療のための腋窩リンパ節郭清後に発症します。下肢では骨盤内臓器(子宮、卵巣、前立腺、大腸)の手術に伴う、骨盤リンパ節および傍大動脈リンパ節の郭清後に発症します。
当科では、リンパケアをおこなう看護師と連携して、まずはスリーブやストッキング等の圧迫療法をはじめとした保存療法を確立し、リンパ管の状態を評価したうえで手術を計画します。
リンパ浮腫に対する従来の外科治療は、体への負担が大きく手術が大掛かりなものが多く、その割には効果が乏しかったり、見た目が著しく悪かったりするものでした。近年、医療技術の進歩、特に顕微鏡下の手術の技術革新により、従来よりも圧倒的に低侵襲な治療法が出てきました。形成外科はもともと、腫瘍を取り去ったあとを埋めるための組織移植で、顕微鏡手術に慣れ親しんでいる科です。顕微鏡手術を応用したリンパ浮腫の外科治療について、これからご説明いたします。
・リンパ管静脈吻合術(LVA)
形成外科で最も多く行っているリンパ浮腫の手術です。
リンパ節郭清後のリンパ浮腫は、リンパの高速道路である集合管を、そのまま東名高速道路に例えるとわかりやすいと思います。
体の中心に向かう方向を東京に向かう方向とお考えください。リンパ節郭清後では、東名東京インターが取り去られ、高速道路経由では首都高に行けなくなります。そのため東京へ向かう車は、手前の川崎や横浜で一度高速を降り、市街地の太い道路を抜けてからもう一度首都高に乗り直す必要があります。交通量の少ない状況であれば(リンパ流の少ない状況であれば)これで問題ないのですが、炎症などを原因として交通量が増えれば、高速道路自体も渋滞し、いずれは市街地も渋滞し車があふれるようになってきます。これがリンパ浮腫を発症した状態です。
この状況を軽減するには、渋滞にたどり着く前にほかの通路にバイパスをつくり、交通量を逃がす必要があります。これがリンパ管静脈吻合術です。リンパ集合管を別の通路である血管とつないでバイパスを作ります。リンパ管は最終的に心臓の上で静脈に戻るので、それが早まるだけで問題はありません。
リンパ集合管は高速道路といえど、直径は0.3~0.8mm程度です。これと太さの似た静脈がそばにある場所を狙い、2~5cmほど皮膚を切ってこの2つを顕微鏡下で縫い合わせます。1か所におよそ1時間かかります。全身麻酔および局所麻酔で手術を行っています。局所麻酔の場合、日帰りも可能です。
このリンパ管静脈吻合術の問題点は、バイパスを作るには、肝心の高速道路がある程度流れている必要がある点です。リンパ管は渋滞がある程度以上の時間続くと、高速道路そのものが壊れてしまい車線が細くなってしまいます。細くなり、もう流れていないリンパ管は、せっかく静脈とつないでも効果がありません。ですので、術前には外来でリンパ管の機能を見る検査としてICGリンパ管造影を行います。ICGは染料の名前です。手足の指の又に染料を注射してその移動を特殊なカメラで追っていきます。注射直後と数時間後を観察します。リンパ集合管機能が保たれていればまっすぐに管が映りますが、ダメージがあると段階を追ってぼやけて映ります。リンパ管静脈吻合術は基本的にはまっすぐに映る部分を対象に行われる手術です。
そして、手術後は渋滞しているところに行く交通量は減りますが、ダメージのある部分を治せたわけではありません。ですから基本的には術後もストッキングなどの圧迫療法の継続は必要であることが多いという点にも注意が必要です。
・その他の外科治療
上記の通り、リンパ管静脈吻合術だけではある程度進行したリンパ浮腫には対応できません。
最近では顕微鏡手術により正常なリンパ組織を移植する治療の報告が確立されてきています。内訳としてはリンパ節移植、大網移植があります。
当科でもより幅広い患者さんへ治療を提供するため、前向きに取り組んでいこうと考えております。
頭頸部の再建
首と頭を合わせて頭頚部といいます。
口に代表されるように、表に皮膚、裏に粘膜のある複雑な構造をしています。一度取り去ってしまうとまわりの組織で補うことができず、体のほかの部分からの組織移植を要することが多い部分です。皮膚や粘膜であれば大腿部やおなかから、骨が必要な場合には下腿の外側から採取して移植する場合があります。
外傷後の再建
外傷(けが)で皮膚や体の一部を失うこともあります。縫い閉じられれば問題は大きくなりませんが、けがが広かったり、腱や骨などの重要な組織が覆いきれなかったりするときは、悪性腫瘍の再建と同様に体のほかの部分から組織を移植する必要があります。
乳房再建
乳がんの治療により失われた乳房を取り戻す手術です。
乳房再建手術の時期により一次再建と二次再建に分けることができます。また、自分の組織の移植(自家組織)によるものとインプラントによるものに大別されます。
①一次再建(同時再建)
乳がんの手術と同時に乳房再建術を始める方法です。当院ではティッシュエキスパンダー(組織拡張器)を乳がんの手術に引き続いて入れ、手術後、半年以上の期間をかけて皮膚を伸ばし、シリコーン・インプラントやご自身の組織に入れ替えて乳房を再建します。乳がん手術後にすでにある程度のふくらみができており、徐々に大きくできるため乳房の喪失感が少ないことや、2回分の手術が1回で終わるため、手術回数が少なくて済むことがメリットです。一方でエキスパンダー挿入術の合併症(感染による取出しなど)が二次再建よりも多少多くなることが知られています。また、エキスパンダーと放射線治療の相性が良くないことから、当科では術後に放射線治療を要さないと思われる病期の方を一次再建の対象としています。
手術をあまり急がなくてもよい性質の乳がんの方には、乳癌手術と同時にご自身の組織で再建をする方法もあります。詳しくは外来主治医にご相談ください。
②二次再建
乳がんの手術が終わったあとで、時期を改めて乳房再建に着手する方法が二次再建です。全乳房切除後の再建や、部分切除術(温存術)後の変形の修正を含みます。再建方法はさまざまであり、乳房の大きさや治療の経過により、おすすめできる方法は変わります。一回の手術で済む方法や一次再建同様に2回の手術に分ける方法、複数回の脂肪吸引・注入により再建する方法等があります。乳腺科主治医の判断のもと、何年経過しても再建は可能ですので、ご相談ください。
[乳房再建の方法]
1)人工物による再建(シリコーン・ブレスト・インプラント法)
シリコーン・ブレスト・インプラントを使って乳房を再建します。
手術時間や入院期間が短く、からだのほかの部位に傷をつける必要もないなど、負担が少ない点が最大のメリットです。一方であくまで自分の体ではない「異物」であり、ひとたび細菌感染をおこすと(数%の頻度)交換や取り出す手術が必要となります。
また、長期に見ると硬くなったり(被膜拘縮)、壊れたりすることも事実です。また、従来のテクスチャードタイプ(表面がざらざら)のインプラントでは、低率ながらも特殊なリンパ腫の発症があることがわかってきたため、2019年7月に新規の販売が停止されました。
当科では、その後発売されたスムースタイプ(表面がつるつる)のインプラントとテクスチャードタイプのインプラントを用いた再建を提供しております。なお、現在従来型のインプラントが挿入されている方については、世界的にも経過観察が標準的です。
詳細は【こちら】をご覧ください。
2)自家組織による再建
自分の組織を移植して、乳房を再建する方法です。
手術時間や入院期間はシリコーン・ブレスト・インプラント法と比べて長くなります。からだの他の部位にキズをつけることとなりますが、人工物と異なり、劣化したり、破損したりすることがありません。負担は大きい分、「一生もの」の再建ということができます。
組織を移動する際に、一度切り離して顕微鏡下に血管をつなぐ手技が必要になる術式が多いのも特徴です。この血管が詰まり、移植した組織が生着しない可能性が2~3%あります。
当院で行っている再建法には以下の方法があります。
・下腹部の皮弁
おなかの中心寄りにある、腹直筋の中を通る血管とその枝を取り出し、へそより下の皮膚と皮下脂肪を移植する方法で、深下腹壁動脈穿通枝皮弁(DIEP皮弁)と呼ばれています。腹直筋の大部分は温存されます。最も多くの組織量を移動することができ、万能な方法と言えます。大きな乳房や下垂のある乳房にも十分対応することができます。反面キズは30cm以上であり、比較的負担が大きいと言えます。また、生涯で一回しか取れませんが、左右同時であれば半分に分けて両側の再建も可能です。おなかに帝王切開や虫垂炎等、手術のキズがある方でも(タテでもヨコでも)対応可能である場合がほとんどですのでご相談ください。
・大腿内側の皮弁
太ももの内側から後方の、ややたっぷりとした組織のある部位を移植する方法です。代表的なものとして、大腿深動脈穿通枝皮弁(PAP皮弁)があります。負担が比較的軽く、左右2つの組織が採取可能であることが特徴です。DIEP皮弁に比べると、移植できる皮膚や組織の量は少ないため、比較的小ぶり~中くらいの大きさの乳房の再建にむいています。
・腰の皮弁
骨盤の後ろ付近の組織を移植する方法です。組織量に個人差があり、おなかにほとんど厚みがない方でも十分な量の組織が得られる場合があります。腰動脈穿通枝皮弁(LAP皮弁)と呼ばれます。つけられる皮膚量が少ないため、エキスパンダーを挿入してからの入れ替えにむいています。血管の長さは短く、血管の移植を要する場合もあります。おしりの上のほうの感覚が鈍くなることがあります。
・背中の皮弁
背中の筋肉である広背筋を用いた皮弁です。広背筋は失っても日常生活に支障はないとされています。中程度までの大きさの乳房の再建に適しています。血管をつなぐ手技がなく、手術手技としては比較的簡便です。上の3つに比べ、筋肉を一つ犠牲にすることが特徴で、移植後使われなくなる筋肉がやせていくため、最終的な大きさの予測がやや困難であると言えます。
以上、乳房再建について時期や術式の違いにより説明してまいりました。
ライフスタイル、ライフステージによって、乳房再建の目的と、それにかけられる時間は様々です。今の自分に最も適した再建方法を選択するお手伝いをし、提供することを目指しています。
リンパの再建
リンパ浮腫の症状の軽減を目的とした再建術です。
上肢では主に乳がんの治療のための腋窩リンパ節郭清後に発症します。下肢では骨盤内臓器(子宮、卵巣、前立腺、大腸)の手術に伴う、骨盤リンパ節および傍大動脈リンパ節の郭清後に発症します。
当科では、リンパケアをおこなう看護師と連携して、まずはスリーブやストッキング等の圧迫療法をはじめとした保存療法を確立し、リンパ管の状態を評価したうえで手術を計画します。
リンパ浮腫に対する従来の外科治療は、体への負担が大きく手術が大掛かりなものが多く、その割には効果が乏しかったり、見た目が著しく悪かったりするものでした。近年、医療技術の進歩、特に顕微鏡下の手術の技術革新により、従来よりも圧倒的に低侵襲な治療法が出てきました。形成外科はもともと、腫瘍を取り去ったあとを埋めるための組織移植で、顕微鏡手術に慣れ親しんでいる科です。顕微鏡手術を応用したリンパ浮腫の外科治療について、これからご説明いたします。
・リンパ管静脈吻合術(LVA)
形成外科で最も多く行っているリンパ浮腫の手術です。
リンパ節郭清後のリンパ浮腫は、リンパの高速道路である集合管を、そのまま東名高速道路に例えるとわかりやすいと思います。
体の中心に向かう方向を東京に向かう方向とお考えください。リンパ節郭清後では、東名東京インターが取り去られ、高速道路経由では首都高に行けなくなります。そのため東京へ向かう車は、手前の川崎や横浜で一度高速を降り、市街地の太い道路を抜けてからもう一度首都高に乗り直す必要があります。交通量の少ない状況であれば(リンパ流の少ない状況であれば)これで問題ないのですが、炎症などを原因として交通量が増えれば、高速道路自体も渋滞し、いずれは市街地も渋滞し車があふれるようになってきます。これがリンパ浮腫を発症した状態です。
この状況を軽減するには、渋滞にたどり着く前にほかの通路にバイパスをつくり、交通量を逃がす必要があります。これがリンパ管静脈吻合術です。リンパ集合管を別の通路である血管とつないでバイパスを作ります。リンパ管は最終的に心臓の上で静脈に戻るので、それが早まるだけで問題はありません。
リンパ集合管は高速道路といえど、直径は0.3~0.8mm程度です。これと太さの似た静脈がそばにある場所を狙い、2~5cmほど皮膚を切ってこの2つを顕微鏡下で縫い合わせます。1か所におよそ1時間かかります。全身麻酔および局所麻酔で手術を行っています。局所麻酔の場合、日帰りも可能です。
このリンパ管静脈吻合術の問題点は、バイパスを作るには、肝心の高速道路がある程度流れている必要がある点です。リンパ管は渋滞がある程度以上の時間続くと、高速道路そのものが壊れてしまい車線が細くなってしまいます。細くなり、もう流れていないリンパ管は、せっかく静脈とつないでも効果がありません。ですので、術前には外来でリンパ管の機能を見る検査としてICGリンパ管造影を行います。ICGは染料の名前です。手足の指の又に染料を注射してその移動を特殊なカメラで追っていきます。注射直後と数時間後を観察します。リンパ集合管機能が保たれていればまっすぐに管が映りますが、ダメージがあると段階を追ってぼやけて映ります。リンパ管静脈吻合術は基本的にはまっすぐに映る部分を対象に行われる手術です。
そして、手術後は渋滞しているところに行く交通量は減りますが、ダメージのある部分を治せたわけではありません。ですから基本的には術後もストッキングなどの圧迫療法の継続は必要であることが多いという点にも注意が必要です。
・その他の外科治療
上記の通り、リンパ管静脈吻合術だけではある程度進行したリンパ浮腫には対応できません。
最近では顕微鏡手術により正常なリンパ組織を移植する治療の報告が確立されてきています。内訳としてはリンパ節移植、大網移植があります。
当科でもより幅広い患者さんへ治療を提供するため、前向きに取り組んでいこうと考えております。
頭頸部の再建
首と頭を合わせて頭頚部といいます。
口に代表されるように、表に皮膚、裏に粘膜のある複雑な構造をしています。一度取り去ってしまうとまわりの組織で補うことができず、体のほかの部分からの組織移植を要することが多い部分です。皮膚や粘膜であれば大腿部やおなかから、骨が必要な場合には下腿の外側から採取して移植する場合があります。
外傷後の再建
外傷(けが)で皮膚や体の一部を失うこともあります。縫い閉じられれば問題は大きくなりませんが、けがが広かったり、腱や骨などの重要な組織が覆いきれなかったりするときは、悪性腫瘍の再建と同様に体のほかの部分から組織を移植する必要があります。
傷をきれいに治す
新鮮外傷、新鮮熱傷
切り傷、やけどです。
各種縫合法や薬剤、創傷被覆材などによって、傷をできるだけきれいに治します。
瘢痕、瘢痕拘縮、肥厚性瘢痕、ケロイド
傷が治ったあとも傷跡が目立つ場合は形成外科で治療いたします。
幅の広い傷跡(瘢痕)については、形成外科の縫合技術で切除、縫い直しを行います。傷跡がひきつれを伴い、体や関節の動かしにくさがある場合には、これを切り取ったうえで、皮膚を互い違いに入れ替えたりして伸びをよくします(瘢痕拘縮形成術)。場合によっては植皮や組織移植を考慮します。
赤く残った傷(肥厚性瘢痕・ケロイド)についても、場合によっては上記のように手術を行います。テープや注射により、赤みを落ち着ける方法もあります。
切り傷、やけどです。
各種縫合法や薬剤、創傷被覆材などによって、傷をできるだけきれいに治します。
瘢痕、瘢痕拘縮、肥厚性瘢痕、ケロイド
傷が治ったあとも傷跡が目立つ場合は形成外科で治療いたします。
幅の広い傷跡(瘢痕)については、形成外科の縫合技術で切除、縫い直しを行います。傷跡がひきつれを伴い、体や関節の動かしにくさがある場合には、これを切り取ったうえで、皮膚を互い違いに入れ替えたりして伸びをよくします(瘢痕拘縮形成術)。場合によっては植皮や組織移植を考慮します。
赤く残った傷(肥厚性瘢痕・ケロイド)についても、場合によっては上記のように手術を行います。テープや注射により、赤みを落ち着ける方法もあります。
母斑、血管腫、良性腫瘍
ほくろ、あざの治療です。
ほくろや良性腫瘍は、なるべくあとが目立ちにくいように切除します。
あざについては、当院ではレーザーがないため他院への紹介を考慮致します。
静脈奇形や海綿状血管腫についても同様に他院への紹介を考慮致します。
ほくろや良性腫瘍は、なるべくあとが目立ちにくいように切除します。
あざについては、当院ではレーザーがないため他院への紹介を考慮致します。
静脈奇形や海綿状血管腫についても同様に他院への紹介を考慮致します。
学会・講演会活動
当科では、地域医療の活性化や全国的な治療水準の向上を目指し、これまで培ってきた技術や最新の治療についてを各種学会やセミナーなどで積極的に情報発信をしています。
| 日時 | 種別 | 学会名/イベント名 | 演題名 | 演者名 |
| 【学会】 | ||||
| 3/3/2019 | 座長 | 第3回日本リンパ浮腫学会 | パネルディスカッション2「外科治療の効果と限界」 | 棚倉健太 |
| 5/15/2019 | パネルディスカッション (ラウンドテーブル) |
第62回日本形成外科学会学術集会 | 医師に対するリーダーシップ、マネジメント教育とその機会 | 棚倉健太 |
| 5/16/2019 | 教育口演 | 第62回日本形成外科学会学術集会 | video session(人工物乳房再建) | 棚倉健太 |
| 5/16/2019 | ランチョンセミナー | 第62回日本形成外科学会学術集会 | 人工物による乳房再建の基本 サイズ選択のポイント | 棚倉健太 |
| 7/11/2019 | ランチョンセミナー | 第27回日本乳癌学会学術総会 | 知っておきたい!乳房再建最前線~患者さんのQOL向上のためにできること~ | 棚倉健太 |
| 7/12/2019 | ビデオシンポジウム | 第27回日本乳癌学会学術総会 | 乳房切除・再建は当科ではこうやる 日本のHigh Volume Centerでの乳腺・形成共同診療 | 棚倉健太、宮城由美、他3名 |
| 10/10/2019 | シンポジウム | 第7回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会 | 人工物再建における放射線照射症例の中期成績 一次再建におけるPMRT症例を中心に |
棚倉健太、今井智浩、他8名 |
| 10/10/2019 | ランチョンセミナー | 第7回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会 | macrofill®で行う患者に寄り添う乳房再建 | 棚倉健太 |
| 10/10/2019 | 一般口演 | 第7回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会 | Laser Speckle Imagingの乳腺領域への応用 -NSMを中心に- | 棚倉健太、他14名 |
| 10/10/2019 | 緊急セッション | 第7回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会 | BIA-ALCL | 棚倉健太 |
| 10/18/2019 | シンポジウム | 第52回日本内分泌外科学会学術集会 | 遺伝性乳癌予防切除後の再建術 | 棚倉健太 |
| 11/29/2019 | ビデオセッション | 第46回日本マイクロサージャリー学会学術集会 | 1人でもできる!ドナーサイトもきれいなPAP皮弁挙上 | 棚倉健太、他8名 |
| 【国際学会】 | ||||
| 9/21/2019 | E-poster | 米国形成外科学会 Plastic Surgery The Meeting 2019 | A Low-Cost Training ModelFor Harvesting of Deep Inferior Epigastric Artery Perforator FlapUsing Pig Belly Meat | Kenta Tanakura, Tomoyuki Yano,Tomohiro Imai1,他5名 |
| 【講演会(一般)】 | ||||
| 8/30/2019 | 講演 | HOPE NOAH(深圳) | 形成外科・再建外科のご紹介 | 棚倉健太 |
| 8/31/2019 | 講演 | HOPE NOAH(広州) | 形成外科・再建外科のご紹介 | 棚倉健太 |
| 11/20/2019 | 講演 | マンマチアー委員会第112回チアー活動 | 乳房再建 シリコン・インプラントはどうなる? | 棚倉健太 |
| 12/8/2019 | 講演 | 第6回E-BeC特別セミナーin東京・四谷 | インプラントがリコール!?-リコールの原因と最新の自家組織再建- | 棚倉健太 |
| 【講演会(医師)】 | ||||
| 2/16/2019 | 講演・座長・司会 | 第4回アラガンブレストミーティング | 当科でのデータ処理 | 棚倉健太 |
| 3/22/2019 | 教育口演 | 乳房再建セミナーin鹿児島 | 一次二期再建のためのNSM/SSM -がん研での術式の変遷- | 棚倉健太、宮城由美 |
| 【招待手術】 | ||||
| 8/21/2019 | 招待手術手技実演 | 招待手術 | 深圳人民病院にて乳房インプラント、乳房縮小術デモ | 棚倉健太 |
部長
棚倉 健太(たなくら けんた)

学会認定
日本専門医機構認定形成外科専門医
日本形成外科学会形成外科領域指導医
日本形成外科学会
再建・マイクロサージャリー分野指導医
小児形成外科分野指導医
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会
評議員
エキスパンダー/インプラント責任医師
日本乳癌学会
評議員
専門分野
再建(乳房、体幹(腹壁、ヘルニアを含む)、四肢)
リンパ浮腫
マイクロサージャリー
創傷治癒
日本専門医機構認定形成外科専門医
日本形成外科学会形成外科領域指導医
日本形成外科学会
再建・マイクロサージャリー分野指導医
小児形成外科分野指導医
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会
評議員
エキスパンダー/インプラント責任医師
日本乳癌学会
評議員
専門分野
再建(乳房、体幹(腹壁、ヘルニアを含む)、四肢)
リンパ浮腫
マイクロサージャリー
創傷治癒
科長
倉元 有木子(くらもと ゆきこ)

学会認定
日本専門医機構認定形成外科専門医
日本形成外科学会
再建・マイクロサージャリー分野指導医
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会
評議員
エキスパンダー/インプラント責任医師
日本創傷外科学会専門医
専門分野
再建(乳房、頭頸部、体幹、四肢)
リンパ浮腫
マイクロサージャリー
創傷治癒
日本専門医機構認定形成外科専門医
日本形成外科学会
再建・マイクロサージャリー分野指導医
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会
評議員
エキスパンダー/インプラント責任医師
日本創傷外科学会専門医
専門分野
再建(乳房、頭頸部、体幹、四肢)
リンパ浮腫
マイクロサージャリー
創傷治癒
医長
早坂 李枝(はやさか りえ)

学会認定
日本専門医機構認定形成外科専門医
専門分野
再建(乳房、頭頚部)
手の外科
マイクロサージャリー
一般形成
日本専門医機構認定形成外科専門医
専門分野
再建(乳房、頭頚部)
手の外科
マイクロサージャリー
一般形成
医員
川口 謙太郎(かわぐち けんたろう)
学会認定
日本専門医機構認定形成外科専門医
専門分野
形成外科一般
日本専門医機構認定形成外科専門医
専門分野
形成外科一般
実 績(2024年)
| 手 術 件 数 | 511例 |
| 下腹部の穿通枝皮弁(DIEP)による乳房再建術 | 28例 (うち両側 4例) |
| 大腿内側部の穿通枝皮弁(PAP)による乳房再建術 | 11例 |
| インプラントによる乳房再建術 | 37例 |
| 組織拡張器を用いた乳房再建術 | 52例 |
| リンパ管静脈吻合術 | 14例 |
| 顔面骨骨折 |
8例 |
| 他科合同再建手術(舌、上下顎、食道、腹壁) | 6例 |
| 遊離皮弁総計 | 53皮弁 |
《 主な手術の予定入院日数 》
| 手術・検査・処置名 | 予定入院日数 | 説明 |
| 下腹部の穿通枝皮弁(DIEP)による乳房再建術 | 術後平均8.2日 | 腹直筋から栄養血管のみを剥離し、皮弁を作成し乳房を再建します。採取面積が広く幅広い再建に対応可能です。 |
| 大腿内側部の穿通枝皮弁(PAP)による乳房再建術 | 術後平均6.1日 | 大内転筋内を走行する大腿新動脈の皮膚穿通枝のみを剥離し、皮弁を作成し乳房を再建します。採取部が大腿内側後方で目立たず、両側採取可能であり、若年者にも進めやすい方法です。 |
外来診療表
当科の外来診療表はこちらからご覧いただけます。
外来診療表はこちら
外来診療表はこちら